電話 ~その1~
2016.12.23 岡田定晴
| あの日に帰れたら(作曲:Amacha) |
 初めて自宅に電話が設置されたのは、私が小学校3年生のころ、昭和36年のことでした。
黒いずっしりした電話機でした。電話機の中央には、回転式の円形のダイヤルが配置され、右上の1から左下の9や0という数字の上には穴が開いていました。
円形のダイヤルの中央には、黄色地の丸い紙の上に、確か「受話器を耳にあててツーという発信音を確かめてからダイヤルを廻してください。」
という主旨のメッセージが書かれていました。そのとき、発信音の「信」を何と読んで良いのか、また「発信音」の意味もわかりませんでした。
初めて自宅に電話が設置されたのは、私が小学校3年生のころ、昭和36年のことでした。
黒いずっしりした電話機でした。電話機の中央には、回転式の円形のダイヤルが配置され、右上の1から左下の9や0という数字の上には穴が開いていました。
円形のダイヤルの中央には、黄色地の丸い紙の上に、確か「受話器を耳にあててツーという発信音を確かめてからダイヤルを廻してください。」
という主旨のメッセージが書かれていました。そのとき、発信音の「信」を何と読んで良いのか、また「発信音」の意味もわかりませんでした。
広告
受話器は手に持つとずっしり重く、電話機本体には叩けば鳴る金属製のベルが内蔵されていました。電話の呼び出し音は、このベルが電磁石で叩かれるので、 驚くほどけたたましい音でキンキン鳴り響きました。電話機が鳴り出すと、びっくりするほどでした。特に夜は、こんな時間に何事かと思いました。 ですから、よほど緊急な用事でもない限り、電話は昼にかけるものでした。受話器からどうして音が聞こえるのか、自分の声がどうして相手に伝わるのか 理解できませんでした。小学校の理科の時間に糸電話を作って遊んだので、これを電気仕掛けにしたものだろうと考えていました。 両親が家に居る時は良いのですが、居ないときにベルが鳴ったらどうしようかと心配でした。
自宅に電話が設置される以前、母は、手紙や葉書きで頻繁に祖父や祖母と文通をしていました。私が小学校2年生の時、母の叔母が亡くなった時は、電報で連絡がありました。 電話のある相手に連絡をする必要があるときは、200mくらい先にあった公衆電話に電話をかけに行っていました。 店先に置かれた公衆電話ではなく、木製の小屋、電話ボックスの中に設置された公衆電話でした。 今のように、透明なアクリルで囲われたボックスではなく、木の板で囲まれていて、大人の顔の高さに小さな窓があって、電話ボックス内から 外が見えるようになっていました。母と一緒に電話ボックスに入ると、私には周囲の風景が見えなくなってしまいました。
自宅にある黒電話のお陰で、簡単な要件は自宅の電話で済ませることができるようになり、生活は便利になりました。 この黒電話は、私が就職のために実家を離れる昭和50年になるまで、一度モデルチェンジがあったのですが、 色は黒のままで多少軽量化されただけでした。街角には、赤やピンクの電話が商店の店先に置かれていました。 これも、モデルチェンジで軽量化はされたようですが、ずっと10円電話で同じままでした。 テレビで100円電話があることを知りましたが、生活圏内には無く、テレホンカードが使える電話は未だありませんでした。
今と違って、10数年も同じ電話を使い続ける変化のない時代でした。

 平成の徒然草ICT版
平成の徒然草ICT版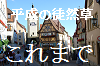 これまでのブログ
これまでのブログ