シェアオフィス
2017.11.28 岡田定晴
| ソワールへ続く道(作曲:Amacha) |
 コストを抑えて都心にオフィスを構えることができる時代になりました。シェアオフィスは、
①インターネットに接続した端末で仕事ができるようになり、②セキュリティを保って複合機を共有することができるようになり、
③離れた場所からオフィスの監視や管理ができるようになるなど、ICT(情報通信技術)の進歩の恩恵を最大限に受けたオフィスの形態だと思います。
コストを抑えて都心にオフィスを構えることができる時代になりました。シェアオフィスは、
①インターネットに接続した端末で仕事ができるようになり、②セキュリティを保って複合機を共有することができるようになり、
③離れた場所からオフィスの監視や管理ができるようになるなど、ICT(情報通信技術)の進歩の恩恵を最大限に受けたオフィスの形態だと思います。
昭和50年代の終わりのころ、私は仕事の関係で、都心にある会社のオフィスを尋ねたことがあります。 私が想像していたような会社の構えはありませんでした。マンションのエントランスに居るガードマンに行先を告げて、 その一室に向かいました。マンションは、生活のために居住する場所と思っていたのですが、 そこでは、コンピュータを駆使して開発が行われていました。また、営業活動の拠点としても使われていました。 その時、仕事の中身のことよりは、「マンションをこんな風に利用することができるのか」ということに感心しました。 実質的に仕事が出来れば、見掛けを気にしなくても、同じことであると思いました。
 そんな経験をした昭和の終わりの頃から、30年くらい経過した頃、今から3~4年前のことですが、
都心にあるシェアオフィスのことを耳にしました。「知らない人同士が同じ空間を共有し、パソコンに向かって
仕事をしている。会社の所在地は、都心のそのシェアオフィスにある。」という内容でした。
都心にオフィスを借りて、その場所を会社の所在地とすることは、大変にお金がかかることと思っていましたが、
インターネットで調べると、確かにシェアオフィスとかレンタルオフィスというものがあって、
想像していたよりもはるかに安価に借りられることがわかりました。
そんな経験をした昭和の終わりの頃から、30年くらい経過した頃、今から3~4年前のことですが、
都心にあるシェアオフィスのことを耳にしました。「知らない人同士が同じ空間を共有し、パソコンに向かって
仕事をしている。会社の所在地は、都心のそのシェアオフィスにある。」という内容でした。
都心にオフィスを借りて、その場所を会社の所在地とすることは、大変にお金がかかることと思っていましたが、
インターネットで調べると、確かにシェアオフィスとかレンタルオフィスというものがあって、
想像していたよりもはるかに安価に借りられることがわかりました。
広告
 こうしたことがあって数年後の今、私はシェアオフィスで仕事をしています。
オフィスは、空いていれば座ることのできるフリーアドレスのエリアと、個室があります。
また、社名の表示や小型の郵便受とインターフォンがあるエントランス、小規模な打ち合わせができる
ミーティングルーム、そのほかロッカールームやラウンジ、トイレや給湯室があります。
高速インターネット回線、LANケーブル、無線LAN、インターフォン(電話機)、
コピー・印刷・スキャンのできる複合機、シュレッダー、飲料の自動販売機、ウォーターサーバー、
空気清浄機、防犯カメラ、ICカードで開錠するセキュリティドアなどが備わっています。
住所の使用や法人登記も可能です。
多くの人が設備をシェアすることによって、当初必要になる経費や、普段のランニングコストを
抑えて、都心にオフィスを持つことができるのです。
こうしたことがあって数年後の今、私はシェアオフィスで仕事をしています。
オフィスは、空いていれば座ることのできるフリーアドレスのエリアと、個室があります。
また、社名の表示や小型の郵便受とインターフォンがあるエントランス、小規模な打ち合わせができる
ミーティングルーム、そのほかロッカールームやラウンジ、トイレや給湯室があります。
高速インターネット回線、LANケーブル、無線LAN、インターフォン(電話機)、
コピー・印刷・スキャンのできる複合機、シュレッダー、飲料の自動販売機、ウォーターサーバー、
空気清浄機、防犯カメラ、ICカードで開錠するセキュリティドアなどが備わっています。
住所の使用や法人登記も可能です。
多くの人が設備をシェアすることによって、当初必要になる経費や、普段のランニングコストを
抑えて、都心にオフィスを持つことができるのです。
 このオフィスで、私が最も優れていると思うのは、「誰にも邪魔されず、自分のしたい仕事に集中
できること」です。もちろん、物音や話し声は聞こえてきますが、自分の仕事をディスターブされる
ことはありません。組織の中で働いていたときは、自分のしたいことに集中することができませんでした。
次から次に、人から相談を受けたり、会議に出席したり、判断を求められたり、メールに目を通したり、
昼の食事に付き合ったり(付き合わせたのかもしれませんが)、上司から宿題を出されたり・・・、
自分の時間がありません。自分の仕事は家で片付けて、会社では人のために時間を空けておく
くらいの気持ちがないとやっていられませんでした。
このオフィスで、私が最も優れていると思うのは、「誰にも邪魔されず、自分のしたい仕事に集中
できること」です。もちろん、物音や話し声は聞こえてきますが、自分の仕事をディスターブされる
ことはありません。組織の中で働いていたときは、自分のしたいことに集中することができませんでした。
次から次に、人から相談を受けたり、会議に出席したり、判断を求められたり、メールに目を通したり、
昼の食事に付き合ったり(付き合わせたのかもしれませんが)、上司から宿題を出されたり・・・、
自分の時間がありません。自分の仕事は家で片付けて、会社では人のために時間を空けておく
くらいの気持ちがないとやっていられませんでした。
それなら、都心にオフィスなど借りないで、自宅で仕事をすれば良いのではないかと言われそうですが、 家に居れば、妻から布団を干せだの、買い物に行けだの、孫の面倒を見ろだのと言われて、仕事に集中する 環境を確保することが難しいのです。仕事とプライベートが曖昧になってしまいます。また、通勤時間に 都会の風景を見ることは良い刺激になって、仕事にプラスに作用します。 ですから、私にとってシェアオフィスは、「誰にも邪魔されず、自分のしたい仕事に集中できる場所」なのです。 それと、都心にありますから、銀行・郵便局・法務局・税務署・病院・喫茶店・コンビニ・デパート(書店)・飲食店ほか、 仕事に必要な機能が歩いて直ぐ行ける場所にあります。無駄な時間を費やすことなく、本来の仕事に時間を 振り向けることができます。
 ICT(情報通信技術)が発展し、インターネットに接続された端末があれば仕事のかなりの部分が
実行できるようになり、複数の人が一台の複合機をセキュリティーを確保して共有できるようになり、
また「ICカードで開錠するセキュリティドア」や「防犯カメラ」や「遠隔操作によるオフィスのクローズやオープン」
などでオフィスの安全が確保されるなどの条件が整った今、新しい形態のオフィスが誕生しているのだ、
これが21世紀の今なのだと感じるのです。ICTの進歩を受けて登場した都会のシェアオフィスは、
安価で便利に使え、新しいものを生み出していく創造的な空間になっていました。
ICT(情報通信技術)が発展し、インターネットに接続された端末があれば仕事のかなりの部分が
実行できるようになり、複数の人が一台の複合機をセキュリティーを確保して共有できるようになり、
また「ICカードで開錠するセキュリティドア」や「防犯カメラ」や「遠隔操作によるオフィスのクローズやオープン」
などでオフィスの安全が確保されるなどの条件が整った今、新しい形態のオフィスが誕生しているのだ、
これが21世紀の今なのだと感じるのです。ICTの進歩を受けて登場した都会のシェアオフィスは、
安価で便利に使え、新しいものを生み出していく創造的な空間になっていました。

 平成の徒然草ICT版
平成の徒然草ICT版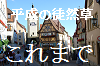 これまでのブログ
これまでのブログ